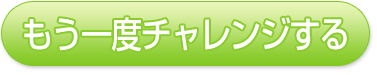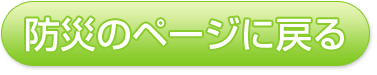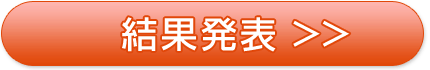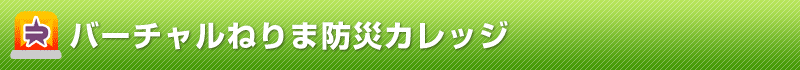
練馬区で起きる可能性がある災害で、正しい組み合わせはどれですか?
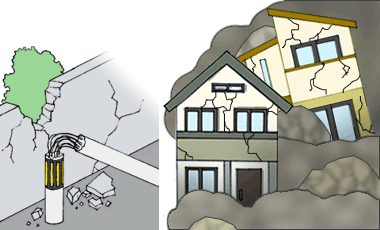 |
|
 |
 日本では、地震はどこでも起きる可能性がありますが、津波は海から離れている練馬区まで届きません(位置の確認は、インターネットの検索サイトから「練馬区 地図」と入れて検索してみましょう)。
 |
 水害も土砂災害も起きます。水害の種類は2つ。内水氾濫(ないすいはんらん)と外水氾濫(がいすいはんらん)です。内水氾濫は、側溝や下水の排水 量だけでは降った雨を処理しきれずに、水がたまってしまう水害で、外水氾濫は河川が決壊・破堤により家屋などを流してしまう水害です。
練馬区では、過去局地的な集中 豪雨で床下・床上に浸水する内水氾濫による被害が起きています。 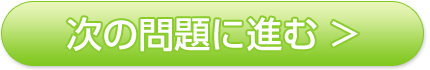 |
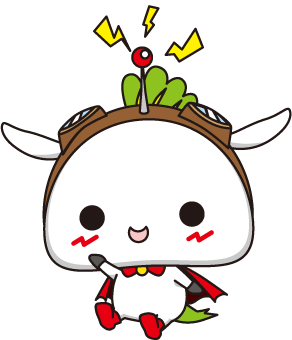 |
次のうち、被害を軽減しにくい災害はどれですか?
 |
|
 液状化とは、地震の揺れにともなって、地下の砂地盤が液体状になる現象です。建物が傾いて倒れたり、土管やマンホールなどが地上に浮き上がったりする被害が出ます。かつて川や田んぼであった場所や、海岸や川のそばの比較的地盤がゆるく、締め固められていない地下水位の高い砂地盤などで起こります。建物を建てる場合には、予め地盤改良や特別な建て方をしない限り、この被害を抑えるのは難しくなっています。
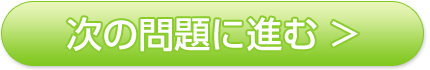 |
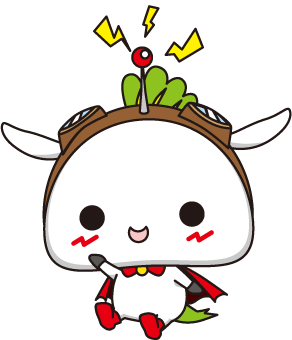 |
 |
 海辺や海に近い川沿いで大きな揺れを感じたら、直ちに高台等に避難しましょう。まずは命を守ることが重要です。東日本大震災では、3階の高さでも犠牲者がでたケースがありますので、より高台に避難しましょう。
また、海辺に出かけるときは、近くに頑丈な高い建物や高台があるかチェックする習慣をつけましょう。
 |
 |
 大雨や地震で地盤がゆるむと、がけ崩れや地すべりなどの土砂災害が起きます。しかし、台風や大雨などの気象情報を常にチェックをし、予め安全な場所に避難
することで、難を逃れることができます。
まずは、天気予報や練馬区が出す情報等を常にチェックするようにしましょう。  |
大地震への備えとして、間違っているのはどれですか?
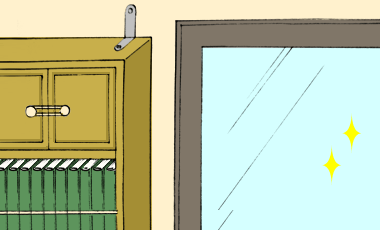 |
|
 |
 平成7年(1995年)1月17日に発生した阪神・淡路大震災で犠牲になった方々の8割が、倒壊した建物や転倒した家具の下敷きになったことによる圧死でした。
家具の転倒防止等の対策は、自分と家族を守るためには重要な対策の一つです。  |
 |
 食器棚や本棚に落下防止対策をとることは、とても有効な対策です。
棚に収まっているものが地震により散乱すると、落下物に足をとられ、歩きにくくなります。 特に、食器類が落下して割れ、破片が飛び散ると、足をケガする原因になります。 ものが落ちてこないように、紐を貼ったり、扉に留め金をつけましょう。  |
次のうち、大地震のあとにまず起こらない出来事はどれですか?
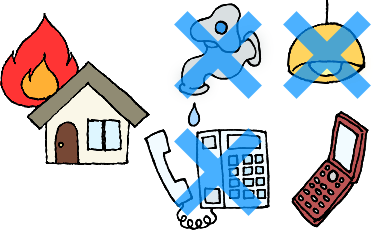 |
|
 |
 どちらも起きます。阪神・淡路大震災では、建築基準法が改正された昭和56年(1981年)以前に造られた建築物や1階が吹き抜けのピロティー建築物等に、特に被害がでました。
ぜひ耐震診断をして、必要に応じて耐震補強をしてください。区では、その費用の一部を助成しています。 一方、火災は、もともと火を使っていたり、ガスが漏れて引火するなどして発生します。  |
 固定電話と同じで携帯電話も通じにくくなると考えられます。一斉に皆が電話をするので規制がかかったり、停電等により、利用することができないかもしれません。
なお、一般固定電話が混雑でつながらないときも、公衆電話は優先電話としてつながる場合があります。緊急の場合以外は発災直後に使うことは避けたいものですが、普段から公衆電話の場所の確認と、小銭を用意しておくとよいでしょう。 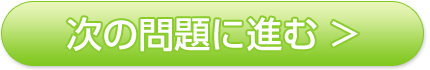 |
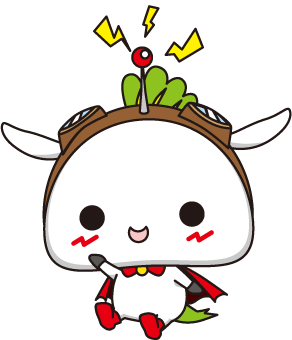 |
地震による大きな揺れを感じたら、 まずどう行動しますか?
 |
|
 |
 揺れの中では、転倒したり、なべのお湯や油がかかって大ケガをする危険があるので、無理は禁物です。最近のガスコンロには、大地震時にガスが自動的に止まる装置が付いているので、危険をおかしてまで消しにいくのはやめましょう。なにかの具合で消えなかったとしても、揺れがおさまってから消すチャンスはあります。
揺れている間は、まず、身の安全を確保しましょう。
 |
 ちょっとした揺れを感じた時点で、すぐになにかが落ちてきたり、倒れてくるような場所からは離れて、安全な場所に移動するか、頑丈な机の下などに入るように習慣づけましょう。
揺れの様子見は非常に危険です。住んでいる家が地震に弱い可能性があれば、外の安全な空間に出るという選択肢もありえます。まずは身の安全を確保してください。 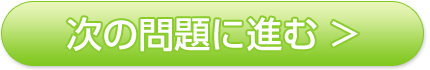 |
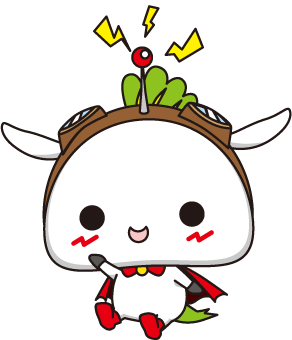 |
 |
 2階にいる場合にはそのまま安全な空間に身を寄せましょう。過去の震災では、木造家屋の1階はつぶれるものの2階はそのままといったケースが多くみられました。
とはいえ、地震から生命・財産とも守るためには、建物の倒壊を防ぐことが最も大切です。建物の耐震性が心配な方は、ぜひ耐震診断をしましょう。  |
地震による揺れを感じたときにたまたま海辺にいました。揺れがおさまったらどう行動しますか?
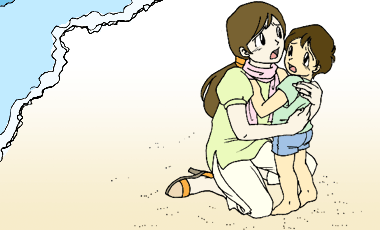 |
|
津波の心配がない街中で、大きな地震を感じました。揺れがおさまってまず取る行動はどれですか?
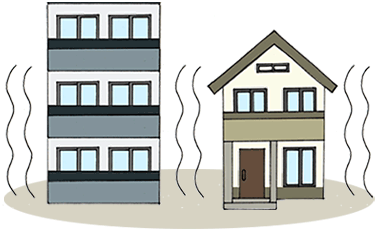 |
|
 |
 119番や110番は、電話の殺到による混乱防止のため、極力避けましょう。さらに電話自体も直後から通じなくなっている可能性が高く、また多くのケガ人、火災が発生するため、消防署も警察署もふだんのような対応ができないということを、覚えておきましょう。
 |
 |
 すり傷などの軽傷であれば、病院に行かずに応急手当ができる体制を自宅やご近所、あるいは地域で整えるようにしましょう。
病院では、時間を争うような大ケガの人が最優先されます。状況によっては、骨折すらも軽症扱いとされる場合があることを覚えておきましょう。 とにかくケガをしないことが大切です。  |
 |
 大地震が発生した場合、鉄道各社は線路等の点検を行い、安全に運行できるか確認できるまで、運行を再開しません。
まずは安全に留まれる場所を見つけること、もしくは職場・学校にいたら、そこに留まるべきです。その場で正確な情報を収集し、時間差で帰宅するようにしましょう。  |
 こうした非常事態では、その時その場でできることをしてください。無理してなにかをしようということではありません。まずはご自身の身の安全確保が第一。そのうえで、周囲の人と協力して安否確認をしたり、ケガをしている人や建物内に閉じ込められている人などの救助等をお願いします。
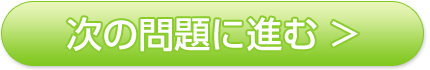 |
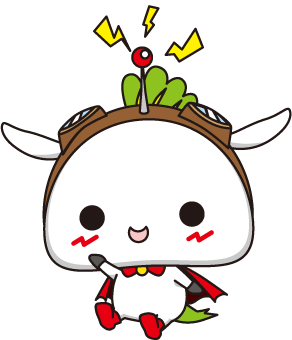 |
大地震のあと、自分の背丈より小さな火が出ていました。もっとも適切な行動は次のどれですか?
 |
|
 |
 火が小さいうちに消火することが大切です。近所や周囲の人と協力して消火しましょう。ただし、例えば、子どもたちだけのグループでいるときに火が出ていることを見つけた場合には、身を守ることを第一に考えて行動してください。離れるときには、火が出ていることを周りの大人に知らせましょう。
 |
 まずは大声で「火事だ」とご近所や周囲の人に知らせるようにしましょう。初期消火ができる範囲は「自分の背より小さい火」とも言われていますが、消火器を集めてきてもらったり、バケツリレーをするなど、消火には周囲の方々の協力が必要になります。
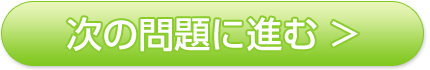 |
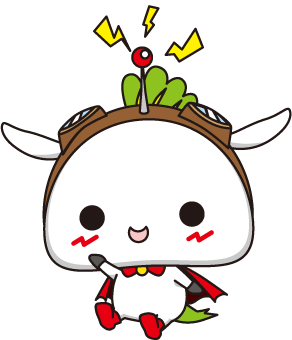 |
 |
 よほど小さな火であれば一人での消火は可能かもしれませんが、近くに油があるなど一人で消火を試みるには危険なケースも考えられます。出火場所などの状況によりますが、「もっとも適切な行動」とは言えません。近所や周囲の人と協力して消火しましょう。
 |
大地震で救出が必要な人やケガ人が多数出ました。どんなケガ人が最も注意が必要ですか?
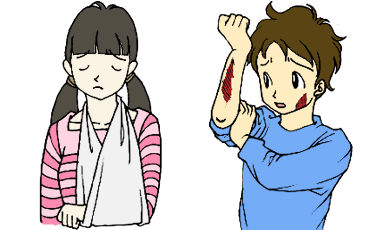 |
|
 |
 火災発生により、皮膚や気管支の熱傷(やけど)が起きることも想定されますが、これが最も注意が必要とは言えません。
ただし、広範囲にやけどを負うと、ショック症状などが出て危険です。至急、病院に搬送する必要があります。  |
 2~3時間を越えて長く足などがはさまれ下敷きになっていた場合、挫滅(クラッシュ)症候群といって、助け出された(圧迫から開放された)その瞬間から体に毒素がまわり始めます。元気そうに見えても至急病院に搬送し治療を受けないと、命に関わります。
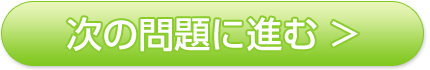 |
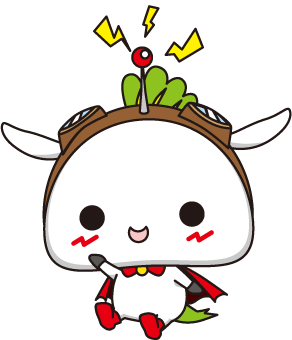 |
大地震のあと、避難が必要でないケースは、次のどのようなときですか?
 |
|
 避難拠点は限られたスペースしかないので、家が倒壊した人や、家に亀裂が入るなどの危険にさらされて、家に戻れない人で一杯になります。避難拠点は決して快適な場所とは言えませんし、電気と水道等が使えないのは、皆同じです。自宅で生活がができるよう、非常用の電源や懐中電灯、水等を備蓄しておきましょう。
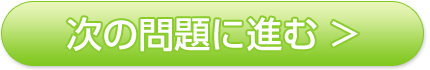 |
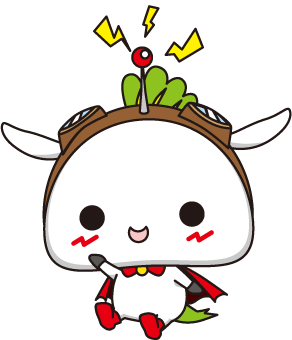 |
大地震で避難が必要なとき区内では、どこに行きますか?
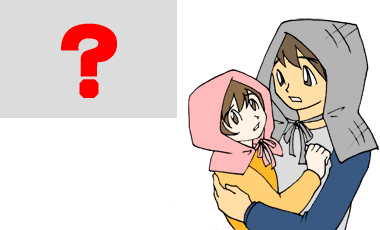 |
|
 区立の小中学校が「避難拠点」として、地域の防災拠点かつ避難場所になります。水・食料の配給拠点、避難生活の支援、各種情報の提供、救助の要請等も行われ、地域の要となります。
避難拠点では、日頃から防災訓練を行っています。ぜひ参加して、いざというときに備えておきましょう。 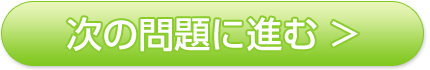 |
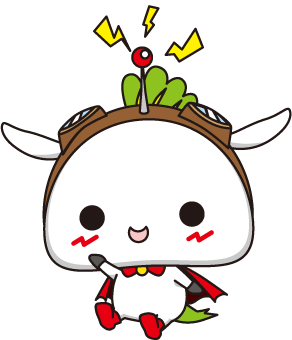 |
大地震の直後、津波の心配のない場所では正しい情報を得て行動することが望ましいといえます。次のうち、もっとも信頼のおける情報源はどれですか?
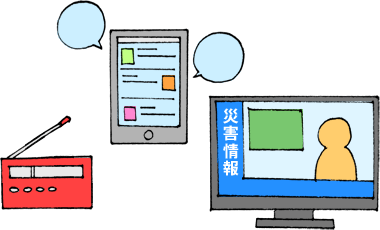 |
|
 |
 インターネット通信網が使えれば有効ですが、災害時に確実に使えるとは限りません。
また、ツィッターなどのソーシャルメディアでは、発信者によっては不確かな情報も流れることがあります。ただし、練馬区や総務省消防庁等、公の機関からの発信は有効です。  |
 |
 発災直後は難しいと思いますが、地域の情報を得るには、避難拠点で得るのが一番です。とはいえ、多くの人が一斉に拠点に訪れると混乱しますので、自治会・町会など地域で行く人を決めて掲示板に貼るなどし、うまく情報共有をするようにしましょう。
 |
会社や学校で突然の大地震に見舞われたときに、備えておくべきことで間違っているものはどれですか?
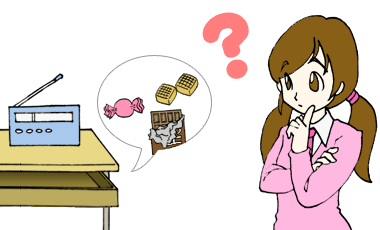 |
|
 |
 会社や学校から自宅まで、電車やバス等の公共交通機関を使わずに帰る訓練は非常に有効です。
帰宅途中の危険な場所を確認し、迂回できる経路を探しましょう。 東京都は、都立施設で水、トイレ、休息場所を提供するとともに、コンビニエンスストア、ファストフード店、ファミリーレストラン、ガソリンスタンド等と協定を結び、休息場所等の提供を行うこととしています。  |
 電車やバス等の公共交通機関は、大地震が発生すると、線路点検のうえ、安全確認ができるまで運転を見合わせます。
すぐには帰宅せずに、交通情報等をよく確認し、安全に帰宅できるようになってから帰宅するようにしましょう。 東京都では条例を定め、事業所で待機できるように食料等を備蓄するように事業者に呼びかけています。 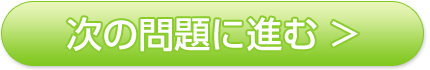 |
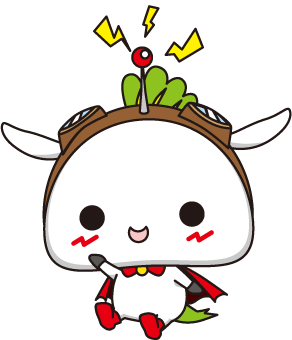 |
 |
 災害用伝言ダイヤル「171」や各携帯電話会社による災害用伝言板を活用して、お互いの安否を確認しあいましょう。
災害等により自宅に帰ることができなくなった場合には、家族全員が知っている場所を集合場所に決めておきましょう。
 |
 |
 大地震が発生すると、日常とは違い、食料等の入手が難しくなる場合があります。
軽量で高カロリーな食料を備蓄しておくことをお勧めします。 学校の場合は、校則でお菓子の持ち込みを禁止している場合があります。先生に確認してから備えましょう。  |
最寄の避難拠点(区立小中学校)に行ったら、地域の方が集まって避難拠点が開設されていました。次のうち最も適さない行動はどれですか?
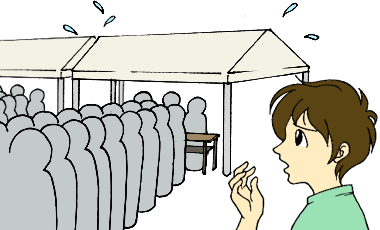 |
|
 |
 各学校では、区の職員や地域住民、教職員が、「避難拠点」運営の訓練をしていますが、これらの方々も被災して、来られない方も多く出ることが想定されま
す。多くの避難者が一斉に来る事態も考えられるため、無事で余力のある方はお手伝いをお願いします。避難拠点のスタッフも、皆さんと同じ区民であり、また、被災者である場合もあります。ご協力をお願いします。
 |
 |
 初めて訪れる場所では、目の不自由な方は勝手がわからず動くことも難しい状態に置かれます。頼りの「音」も、周囲の雑音にかき消されがちです。ぜひ、「なにか手伝えることはありますか?」と声をかけるようにしましょう。
 |